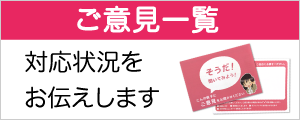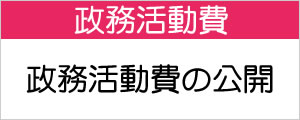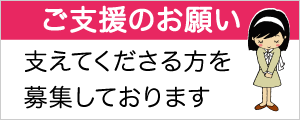(1)歩車分離信号の新設・変更時における視覚障がい者への配慮を
Q 金野桃子 議員 (県民)
令和4年、戸田市内で、近隣に学校、図書館、福祉センター等がある交差点が歩車分離信号に変更されました。
視覚障がい者の方が歩車分離信号に変更したことを認識できず、車両用の信号に合わせて歩行者用が赤信号の中を歩いている場面に、地元市議会議員の方が遭遇し、事故寸前で声を掛けて止めたという出来事がありました。
警察によると、事前に2週間程度立て看板を設置して周知するものの、音響式信号機や音声案内は設置していないそうです。
今回は幸い事故に至りませんでしたが、重大な事故につながる危険があります。
歩車分離信号を新設・変更する場合には必ず音響式信号機を設置し、特に変更する場合には音声案内や福祉団体への周知を徹底すべきと考えますが、警察本部長にお伺いいたします。
A 警察本部長
歩車分離式信号機については、警察庁の指針に基づき、児童、高齢者等の交通の安全を確保する必要がある場所などを対象に、車両及び歩行者の交通量等を調査した上で整備しております。
また、音響式信号機については、警察庁の指針に基づき、視覚障害者関係団体等からの要望を踏まえ、視覚障害の方の利用頻度が高い施設、駅、病院等の周辺において、音響に対する付近住民の御理解を得ながら、整備を推進しているところであります。
県警察といたしましては、今後も歩車分離式信号機の整備に当たり、既設の歩車分離式交差点も含めて、視覚障害の方の利用頻度等も踏まえつつ、必要性や優先度を勘案しながら、音響式信号機の整備を推進してまいります。
次に、「歩車分離式信号機に変更する際の周知」についてであります。
歩車分離式信号機への変更に伴う事前周知については、県警察におきましても重要と認識しております。
導入の時期等を示した立て看板を事前に設置し、利用する方々が安全に通行できるよう配慮をしているところであります。
議員お話しの設置に先立つ音声による案内については、音響式信号機を整備する際と同様に、音声に対する付近住民の御理解を事前に得る必要があることを踏まえますと、音声案内の装置を設置することは困難と考えております。
県警察といたしましては、今後、歩車分離式信号機を整備する際の周知について、福祉団体や市町村を通じてお知らせするほか、整備状況をホームページに掲載するなど、視覚障害の方々に対する情報提供の充実が図られるよう検討してまいります。
(2)一方通行解除をする際、第三者に確認できる方法を
Q 金野桃子 議員 (県民)
県内でマンション建設に伴い、建設会社が警察に道路の一方通行解除を申請しました。これに対して、
地元住民からは一方通行解除を認めないよう求める数百筆の要望書も提出されましたが、警察は①一定の車両制限、②標識の被覆、③警備員の配置等の指導し、申請を認めた事例がありました。ただ、標識に被覆されていなかったのか、現場では工事車両の進入をめぐり、近隣住民とトラブルになったそうです。警察に確認したところ、道路交通法上、一方通行解除については申請書や許可証のような書類はなく、事業者等からの疎明資料に基づき現場調査等を行い、その検討結果を事業者等に口頭で回答するそうです。法律上規定がないため、事業者等に対して書面は出せないというのが警察の見解ですが、一方通行解除は影響が大きく、誤解や摩擦が生じやすいため、警察の検討結果や指導事項が正しく守られているかを確認するためにも、何らかの書面を交付できないか、交付できないとしても各警察署のホームページ上に周知するなど、第三者が確認できる方法を検討できないか、警察本部長にお伺いいたします。
A 警察本部長
一方通行道路における道路工事やマンション建設工事等により、う回路や大型車両の通行場所が確保できないなど、やむを得ない理由がある場合に限り、事業者等からの要請に基づき、必要最小限の範囲で一時的に一方通行の規制の効力を停止する場合があります。
この場合、警察署から要請者に対して、口頭により一方通行解除の可否の伝達を行い、併せて道路標識の被覆等を行わせているところであります。
議員御指摘の書面の交付についてでありますが、一方通行解除の手続は交通規制の効力を一時的に停止するものであり、個々の要請者の権利義務に関するものではないため、許可証等の交付物はなく、口頭によりその可否を伝達しているところであります。
また、ホームページ上での周知についてですが、一方通行の一時解除は、各種工事の進捗状況に合わせて、一時的に必要最小限の範囲で実施されるものであるため、実態が正しく反映されず、誤認されるおそれがあると考えております。
しかしながら、議員お話しのとおり、住民への影響を踏まえ、今後も一方通行規制の効力停止に当たっては、要請者に対して、住民等に対するチラシ等による事前周知を行わせつつ、個々の現場の状況に応じて、誘導のための警備員を配置してもらうなど、交通の安全と円滑に配慮してまいります。
―
【再質問】
Q 金野桃子 議員 (県民)
ホームページヘの掲載は、具体的になぜできないのか、警察本部長に伺う。
A 警察本部長
ホームページにおいて、特定の地域における個別の一方通行規制の一時解除に関する情報を掲載することは、多くの方がご自身と関わりのある情報であると誤認されるおそれがあると考えております。
そのため、地域住民に対するチラシの配布を要請者に行わせるほか、必要に応じて警察署や交番ヘチラシを備え付けるなど、特定の地域の住民の方々に対して直接情報提供を行うことが効果的であると考えております。
県警察といたしましても、情報が必要な方々への周知は重要であると認識しております。今後も適切に情報提供がなされるよう努めてまいります。
次に、要請者が住民に配布するチラシや警備員の配置図等の資料は、一方通行の一時解除を検討する上で必須の資料ではありません。
他方、対象地区の交通の安全と円滑を確保する上では、要請者によりチラシ等が地域住民に適切に配布されることが、効果的であると承知しております。
加えて、一時的に一方通行を解除する際に、警備員や誘導員配置の必要性が認められる場合、要請者に対して、その旨を指導しているところであります。
県警察といたしましては、引き続き、要請者による情報提供が地域住民に対して適切になされるとともに、十分な安全が確保されるよう指導してまいります。



 最新レポートはコチラ
最新レポートはコチラ