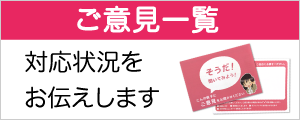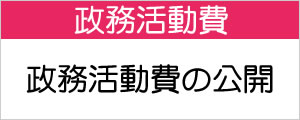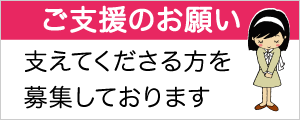Q 金野桃子 議員 (県民)
療育手帳は、知的障害児・者への一貫した指導・相談を行い、各種の援助措置を受けやすくするために、 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所、つまり県立総合リハビリテーションセンターで判定されます。
県内在住で療育手帳をお持ちのお子さんを育てる保護者の方からご相談を頂きました。
療育手帳に記載の再判定の時期を過ぎる1月末に備え、約4か月も前から地元市町村に相談し、障害の特性上日程調整が難しいため、日程を空けて待機をしたそうですが、再判定の時期が過ぎた後も何の連絡もなく、最終的に判定まで6か月を要したとのことです。
再判定の時期を過ぎてからは各種運賃の割引等も使えなかったようです。
担当課からは、人員不足等により判定までに平均5か月程度かかっていると伺いました。
人員不足は理解しますが、判定までに6か月を要し、この間本来受けられるはずの支援が受けられない状況は早急に改善する必要があります。
待機時間を短縮できないか、あわせて、待機中に再判定の時期を過ぎてしまう場合に備えて、判定申請中である旨を証明できる代替証明書のようなものを発行できないか、以上2点を福祉部長にお伺いいたします。
A 福祉部長
療育手帳の判定に当たりましては、心理職による知能検査の他、福祉職による日常生活の調査や精神科医師による診察を行い、総合的に判断する必要がございます。
このため、手帳の交付を申請する方に総合リハビリテーションセンターに来所していただきまして、一人に対して2~3時間をかけて面接や調査等を行う必要がございます。
他方、令和6年度の療育手帳の所持者は6万7 0 3人と、5年前に比べ約1 8パーセント増加しております。
また、手帳の交付後も一定の期間後に再判定を受ける必要があり、増え続ける判定依頼に対してセンターの対応が追い付かず、面接を受ける日までお待たせしている状況でございます。
このため、特に時間を要する知能検査について、センター内で応援体制を執るなど、判定にかかる人員を確保することにより、手帳の判定を受けられる人数を従来よりも約25バーセント増やし、待機時間の短縮を図ってまいります。
なお、申請者が地元の市町村に申請してから長い間何も連絡がなかった、というお話もありましたので、センターが市町村を通じた判定依頼を受け付け次第、面接の日程について市町村との調整を開始し、申請者に今後の予定を速やかにお伝えできるよう改善いたしました。
次に、代替証明書の発行についてです。
手帳に記載されている年月は、次の判定の時期を示すもので、手帳の有効期限ではありませんが、鉄道やバスなどの事業者の中には手帳の有効期限を示すものと捉えている場合もあるようです。
このため、公共交通機関を含む関係機関などに対し、手帳に記載されている年月は有効期限ではなく、手帳としては有効であることを周知徹底してまいります。
また、今後、市町村と調整の上、申請を受け付けた際に、必要に応じて、現在判定手続き中であり、手帳としては有効であることを示す案内文をお渡しするなどして、申請者が不利益を受けることのないようにしてまいります。



 最新レポートはコチラ
最新レポートはコチラ